骨切りのダウンタイムはどれくらい?期間中に現れる主な症状や過ごし方を徹底解説

「張っているエラの骨格を何とかしたい」「しゃくれている顎を何とかしたい」
など、顔の輪郭にコンプレックスを抱いている人には、骨切りがおすすめです。
骨切りは、気になる顔の骨部分を切除したり、移動させたりすることで輪郭を変えることができる施術ですが、気になるのはダウンタイムですよね。
そこで本記事では、骨切りのダウンタイムをはじめ、期間中に現れる症状や術後の過ごし方について詳しく解説します。リスクや副作用についてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
骨切りのダウンタイムはいつまで続くの?主な症状は「腫れ」と「内出血」!種類別の期間を解説

骨切りには、腫れや内出血の症状が現れるダウンタイムがありますが、期間は選択する施術によって異なります。ここで、種類別にダウンタイムの期間を詳しく紹介します。
①おとがい骨切り術のダウンタイム期間
おとがい骨切り術の場合、約1か月で90%程度の腫れ・内出血が改善します。
内出血はあざのようなもので、術直後は赤紫や青色に近い色をしていますが、次第に肌の色に近づき1か月前後で黄色い色味に変化していきます。
腫れや内出血がほぼ完全になくなるのは、3か月程度のことが多いです。
➁頬骨骨切り・骨削り術のダウンタイム期間
頬骨骨切り・骨削り術の場合、約1か月で90%程度の腫れ・内出血が改善します。腫れや内出血がほぼ完全になくなるのは、3か月~6か月程度のことが多いです。
③エラ骨切り術のダウンタイム期間
エラ骨切り術の場合、約1か月で80%程度の腫れ・内出血が改善します。腫れや内出血がほぼ完全になくなるのは3か月~6か月程度のことが多いです。
④下顎枝矢状分割術(SSRO)のダウンタイム期間
下顎枝矢状分割術(SSRO)の場合、約1か月で80%程度の腫れ・内出血が改善します。腫れや内出血がほぼ完全になくなるのは3か月程度のことが多いです。
➄ルフォーI型骨切り術のダウンタイム期間
ルフォーI型骨切り術(上顎骨切り術)の場合、約1か月で85%程度の腫れ・内出血が改善します。腫れや内出血がほぼ完全になくなるのは3か月程度のことが多いです。
⑥Vライン形成術のダウンタイム期間
Vライン形成術・小顔整形の場合、約1か月で80%程度の腫れ・内出血が改善します。腫れや内出血がほぼ完全になくなるのは3か月~6か月程度のことが多いです。

チェックポイントCHECK POINT
ダウンタイムは長期的であると考えておいた方が良い!
クリニックでは、できるだけ出血が出ないように最小限の切開で迅速に施術を行っているため、比較的術後の内出血は短い期間で改善することも多いですが、ダウンタイムに生じる内出血には個人差が大きいため、それぞれ説明した期間はかかると考えおいた方が良いです。
骨切りのダウンタイム中に現れる主な症状

ここで、骨切りのダウンタイム中に現れる主な症状について紹介します。骨切りでは、ダウンタイム中、以下の症状が現れます。
- 口が開きづらくなる(開口障害)
- 皮膚の感覚が鈍くなる・しびれが生じる
- 噛む力が低下(咬筋の筋力低下)
- 皮膚のたるみ
- 火傷・傷跡
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
主な症状①:口が開けづらくなる(開口障害)
骨切りの術後は、口が開けづらくなる症状が出ることがあります。
例えば、頬骨骨切り術の場合、頬骨弓を骨折させて内転させるという操作を行うため、頬骨弓の内側を走る側頭筋の動きに影響がでるリスクがないとはいえません。
頬骨弓を狙い通り正確な位置と方向に内転させた場合は、側頭筋へ影響が生じることはありませんが、内転させる過程で頬骨弓が予定外の場所で折れて中に入り込んでしまった場合などには、偶発的に側頭筋の動きに障害が出る可能性があります。これによって口が開けづらいという症状が発生します。
このような症状が万が一起きてしまった際には、対策として頬骨弓を外側に外転させる器具を使用して外側に向かって折れた骨を整復します。
主な症状➁:皮膚の感覚が鈍くなる・しびれが生じる
骨切りの術後には、皮膚の感覚が鈍くなったり、しびれが生じてしまうこともあります。
例えば、下顎枝矢状分割術(SSRO)の場合、下顎の骨の内面にある歯、歯茎、下唇、頬粘膜などの知覚を支配する下歯槽神経を誤って切断するということはありません。
しかし、骨膜を剥離する過程で傷がついてしまったり、直接神経に触れなかったとしても皮下組織をめくる筋鉤で下顎の骨膜を引っ張っただけで神経に緊張がかかり伸ばされてダメージが生じたりすることもあります。
神経は完全に切断されていなければ必ず回復しますが、ダメージの程度と個人差によって回復に要する期間は約2ヶ月くらいから2年などさまざまです。
もし術中に神経が切断されてしまった場合には、術中に顕微鏡下に神経縫合を行い神経同士の再接合を行います。
術後の神経麻痺の対策としては、ダメージを早く回復させる内服薬を数ヶ月から2年ほどの間、内服します。
主な症状③:噛む力の低下(咬筋の筋力低下)
骨切りの術後には、噛む力が低下することがあります。
頬骨骨切り・骨削り術では、前面へアプローチを行う際に上唇の裏側の粘膜を切開して骨膜下に入り、頬骨弓に向かって剥離を行いますが、その際に咬筋の付着部である頬骨下稜から咬筋を剥がし切断しながら剥離操作を進めます。
この作業によって、場合によっては「咬筋の起始=固定部位」が減るため咬筋の力が低下する可能性があります。
またその他にも、頬骨骨切りを行う際に頬骨弓に付着している咬筋もある程度剥がして頬骨弓が動くようにしてから内転操作を行うので、その際も本来咬筋の動きを支持する骨と筋との接合部が失われるため、操作の合計として嚙む力が低下する可能性があります。
主な症状④:皮膚のたるみ
骨切りの術後には、皮膚のたるみが生じることがあります。例えば、ルフォーI型骨切り術は、鼻の横付近にある上顎骨を短くしたり、後方移動することで目元から口元の長さを調整したりする施術のため、術後は、物理的に目元から口元の皮膚と皮下組織に余裕ができることでたるみが生じることがあります。
このようなたるみが生じるかどうかには個人差があり、一般的に皮膚と皮下組織の厚さに左右される他、年齢にも比例して生じやすくなります。
主な症状➄:火傷・傷跡
骨切りの術後には、火傷による傷跡が残ることがあります。
例えば、下顎枝矢状分割術(SSRO)の場合、口腔内からのみのアプローチで行うため、顔の外面への傷跡は生じませんが、口唇周囲に熱傷が生じ、その跡が色味や膨らみとなって傷跡として残ることがあります。
この傷跡は、術者が手に持つハンドピースが口唇や皮膚に一定時間あたることで生じる低温熱傷によるものです。
予防する措置として、口唇に熱傷予防用のシリコン製のカバーを糸で縫い付けたり、アングルワイダーという口唇を広げる器具を装着することで口唇周囲の皮膚をガードします。
もし仮に熱傷が発生して傷跡が残ってしまった場合は、傷跡ができるだけ目立たなくなる作用を持つ内服薬やステロイド外用テープを早期に使用し、さらに傷跡に膨らみが見られる場合は、ステロイド注射を定期的に傷跡に打ちます。
傷跡の赤みが目立つ際には、赤み取りレーザーによる治療を1年から2年程度継続することで改善します。
骨切りのダウンタイム症状は期間中にどう変化する?「腫れ」を元にした皮膚定着までの経過で解説

ここで、骨切りのダウンタイム症状が期間中にどう変化していくのか、「腫れ」を元にした皮膚定着までの経過を詳しく解説します。
①手術後の腫れは3日間がピーク
骨切りの術後の腫れは、術後3~4日間がピークです。ピークを過ぎると、日毎に腫れは軽快していきます。
➁術後5〜7日後はマスクがあれば目立たないレベル
術後5~7日間ほど経過すると、マスクをしていれば目立たないレベルまで軽快するため、マスクができる職場であれば、1週間ほどのお休みをおすすめします。
③術後10〜14日たてばマスクがなくても大丈夫
術後10~14日ほど経過すれば、マスクを外しても腫れが目立たなくなります。そのため、マスクができない職場の人は、10〜14日間ほど休むのが無難です。
④術後3ヶ月後かけて皮膚がフィットします
術後1ヶ月目くらいになると、腫れはなくなりますが、皮膚がまだ70%くらいしかフィットしていないので、骨が小さくなった分、たるみやぽっちゃり感が気になります。
その後2~3ヶ月かけて、小さくなった骨をめがけて、少しずつ皮膚がフィットしていくため、人と会う機会が多く、尚且つマスクができない職場の人は、1ヶ月間ほどのお休みをおすすめします。
骨切りのダウンタイム期間中は普段の過ごし方が症状を改善するカギに!体温を必要以上に上げるのはNG

ここで、ダウンタイム期間中の過ごし方について紹介します。ポイントは「体温を必要以上に上げないこと」です。ダウンタイム期間中の過ごし方は、以下6つの点に注意して過ごしましょう。
- シャワー・洗髪は当日、洗顔やメイクは翌日から
- 飲酒・運動
- 食事は柔らかいものから
- リンパの流れが良くなる行為は3ヶ月程度控える
- 睡眠時はできるだけ上半身を高くする
- レーザー治療は回復後に
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
ダウンタイム期間中の過ごし方①:シャワー・洗髪は当日、洗顔やメイクは翌日から
骨切り後のダウンタイム期間中は、シャワーと洗髪は当日から行えますが、入浴は術後1週間程度は控えましょう。
洗顔やメイクは当日から可能ですが、できればメイクは腫れがひいてから、洗顔は肌に負担をかけないよう、ゴシゴシ洗うのは避けてください。
ダウンタイム期間中の過ごし方➁:飲酒・運動
飲酒は、傷口からの出血を促進する可能性があるため、術後2週間は避けてください。
運動は、軽い運動や散歩は可能ですが、術後1ヶ月は激しい運動は行わない方が無難です。
ダウンタイム期間中の過ごし方③:食事は柔らかいものから
食事については、口の中に切開の傷があるため、2日間ほどはゼリー食などできるだけ柔らかいものを食べ、刺激物や熱いものの摂取は控えるようにしてください。
また、施術を行った部位の組織はゆっくりと癒着して硬くなってくるので、極端に硬い食べ物を食べるのも避けた方が良いです。
ダウンタイム期間中の過ごし方④:リンパの流れが良くなる行為は3か月程度控える
マッサージなどの血流やリンパの流れが良くなる行為は、出血や腫れを助長しかねないため、3か月程度は控えてください。
ダウンタイム期間中の過ごし方➄:睡眠時にできるだけ上半身を高くする
顔に浮腫みが生じるのを避けるため、睡眠時は、できるだけ上半身を高くするようにしましょう。
ダウンタイム期間中の過ごし方⑥:レーザー治療は回復後に
顔の表面の感覚が完全に回復していない場合にレーザー治療などを行うと、皮膚の火傷を起こす危険があります。そのため、レーザー治療などを受ける場合は、回復してから受けるようにしてください。
骨切りのダウンタイムを抑えるために処方されることが多い薬は3つ!不安なときは頼ってみよう

クリニックでは、ダウンタイムの症状を少しでも抑えるために薬が処方されます。ここで、処方されることが多い薬について紹介します。
処方されることが多い薬①:シンエック
シンエックは、ナチュラルハーブのアルニカモンタナが配合されたサプリメントです。
アルニカモンタナとは、スイスのアルプス地方に生息する野生の植物で、何百年もの間、腫れや傷の治療に使用されてきました。
術後の腫れや内出血の抑制、回復を早める効果が期待できるとして、多くのクリニックで処方されています。
処方されることが多い薬➁:リザベン
リザベンは、現在、唯一国内で保険適応があり、処方されている肥厚性瘢痕、ケロイドに対する治療薬です。
肥厚性瘢痕やケロイドの組織中にある各種炎症細胞が出す化学伝達物質を抑制することにより、痒みをはじめとする自覚症状を抑え、さらには病変自体を沈静化させると考えられています。
リザベンはダウンタイム軽減というより、ケロイドや肥厚性瘢痕に効果が期待できます。
ただし、単独での効果は非常に少ないため、肥厚性瘢痕やケロイドが起こってしまった際には、他の治療と併用する必要があります。
処方されることが多い薬③:紫苓湯
リザベンが飲みにくい人には、柴苓湯が処方されることもあります。
柴苓湯は、小柴胡湯と五苓散を併せた漢方です。
小柴胡湯は、体の免疫機能を調整して炎症を和らげるとともに、体の疲れをとって病気の回復を助けます。
五苓散は、体の働きを高めて、余分な水分を体の外へ出す作用があるため、浮腫に対し有効に働きます。
骨切りにはダウンタイム以外にもリスク・副作用も!施術前にしっかりと理解しておこう

骨切りには、ダウンタイム以外にも、リスクや副作用があります。ここで、骨切りのリスク・副作用について詳しく説明するので、施術前にしっかりと理解しておきましょう。
骨切りには、以下のリスク・副作用があります。
- 骨の段差
- 顎下のたるみ
- 骨壊死
- 左右差
- 顔面神経麻痺
- やりすぎ(下顎角の取りすぎ・上顎骨/下顎枝の切りすぎ)
- 皮膚面の陥没
- 骨の段差(エラが2つあるように見える)
- 関節突起骨折による咬合不全
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
リスク・副作用①:骨の段差
骨切りの施術では、骨の段差が生じることがあります。
例えば、下顎枝矢状分割術(SSRO)の場合、術中に遊離骨片を後ろに下げたり前に出したり、左右にずらしたりすることで、程度の差はあれ、骨の接合面に空隙・段差が生じます。
このような場合には、手指や器具での段差の確認を行い、必要な部分へは専用器具を使用して可能な限り慣らすことによって、段差部をなめらかな面へと変化させます。
リスク・副作用➁:顎のたるみ
骨切りの施術では、顎下にたるみが生じることがあります。
例えば、おとがい骨切り術では、「顎の上下方向を縮める」場合と「顎の先端の位置を下げる」場合に、顎下の皮膚と皮下組織の余剰が発生することで、たるみが生じることがあります。ほとんどの場合、わずかなものなので気にならないケースが多いです。
対策としては、骨切り手術中にナイロン糸を広頚筋に掛けて引き締め、下顎骨にドリルで開けた穴に糸を通して骨に縫い付けるという手法=筋肉縛りがあります。
また、たるみの原因が皮下組織の脂肪である場合は、骨切り術中もしくは後日追加で行う形で、顎下の脂肪吸引でたるみを予防・改善することも可能です。
リスク・副作用③:骨壊死
骨切りの施術では、骨壊死を起こしてしまうこともあります。
例えば、下顎枝矢状分割術(SSRO)の場合、術中、骨切りにより遊離させた骨片が小さすぎて血流が不足してしまった際などには、骨の壊死が生じる可能性があります。
壊死した骨は炎症残存の原因となることがあるため、その際は一部を削り取るなどの処置を行います。
万が一、骨変形をきたしてしまった場合は、人工骨や医療用シリコンプロテーゼによって失われたボリュームを補います。
リスク・副作用④:左右差
骨切りの施術では、左右差が生じてしまうこともあります。
もともと口元やフェイスラインに左右差がある場合、施術によってできるだけ補正するように骨を移動するなどして調整を行いますが、完全に左右対称に仕上がらないことはあり得ます。
もちろん術者は、左右差を極力改善するために外貌を常に確認しながら骨切りを行いますが、術中は麻酔が皮下組織に入っていることに加え、出血によって腫れ・内出血も生じているので、1ミリの狂いもなく左右均等に仕上げることは、熟練した美容外科医であってもかなり難しい作業です。
そのため、クリニックでは術前に左右差の存在を確認し、それぞれの症例に対しての検討を行った上で最も適した骨切り法を選択し、提供しています。
また、術中には、顔貌の左右差を視認しながら骨切りを行うことで、常に左右差の改善に努めています。
リスク・副作用➄:顔面神経麻痺
骨切りの施術では、顔面神経麻痺が生じることもあります。
例えば、ルフォーI型骨切り術の場合、施術によって顔面神経を直接損傷させることは基本的にありませんが、ごく稀に間接的な要因で表情筋の動きが鈍くなる、口にゆがみが生じるなどの神経麻痺が生じることがあります。
術後に神経麻痺が起きた際は、ダメージを早く回復させる内服薬を数ヶ月から2年ほどの間、内服します。
ダメージの程度とダウンタイムには個人差がありますが、おおむね2ヶ月~2年程度で改善することが多いです。
リスク・副作用⑥:やりすぎ(下顎角の取りすぎ・上顎骨/下顎枝の切りすぎ)
骨切りの施術では、下顎角の取りすぎ・上顎骨/下顎枝の切りすぎなどの「やりすぎる」ことによるリスク・副作用もあります。
例えば、エラ骨切り術の場合、「フェイスラインができるだけ細いVラインの形にしたい」と希望する患者さんもいますが、下顎角部は切りすぎてしまうと、「カマキリ」「宇宙人」といった言葉で表現されるような逆三角形の極端なフェイスラインになる可能性があります。
小顔美人の基準として逆三角形のフェイスラインは人気ではありますが、極端になると不自然になるため要注意です。
リスク・副作用➆:皮膚面の陥没
骨切りの施術では、皮膚面が陥没してしまうこともあります。
例えば、エラ骨切り術の場合、施術を行う際に咬筋切除の操作を合わせて行うクリニックがあります。
咬筋切除は骨に操作を加えずともフェイスラインに変化を加えることができる施術ですが、支配神経である三叉神経の枝がダメージを受けるなどした場合、咬筋が均一にボリュームダウンせず、表から見た際に一部がクレーター状に陥没した仕上がりなる恐れがあります。
リスク・副作用⑧:骨の段差(エラが2つあるように見える)
エラ骨切り術の場合、下顎角を切落とすことが最も重要ですが、下顎角を落とす角度によっては、落とした骨の前後で角が生じ、エラが新たに2つ生じたような状態になることがあります。
下顎角は、上から覗き込むと視線が骨面と平行に入るため、非常に全体像がつかみにくく、角を滑らかに落とすのが難しい部位ですが、仮に角が生じたとしても、そこをさらに骨切りしたり、あるいは切らないまでも専用機器で丸めたりすれば、かなり角張った感じを緩和することはできます。
リスク・副作用➈:関節突起骨折による咬合不全
エラ骨切り術の場合、下顎角の骨切り時に、骨切りラインが上方に切れ上がってしまい、下顎枝の関節突起を骨折させてしまうことがあります。これによって開口障害や前歯が開くなどの咬合不全状態が発生する可能性があります。
術中に、骨切りのラインを何度もデンタルミラーで確認しながら操作を加えることで回避できるトラブルではありますが、生じるリスクはゼロではありません。
万一このような骨折が発生してしまった場合は、その場でチタンプレートとスクリューを使って骨折部位を整復固定します。
ダウンタイムのある骨切りだからこそクリニック選びは慎重に!おすすめのクリニックも紹介

ここで、骨切りができるクリニックの選び方について紹介します。
骨切りはダウンタイムがあるため、クリニックは慎重に選びましょう。クリニック選びのポイントは、以下の3つです。
- 実績や経験が豊富な医師が在籍しているか
- アフターフォロー体制は整えられているか
- カウンセリングは丁寧か
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
クリニックの選び方①:実績や経験が豊富な医師が在籍しているか
骨切りの施術を受ける場合は、実績や経験が豊富な医師が在籍しているかを確認しましょう。
骨切りは、リスクもあるため、高い技術力を持つ医師や経験豊富な医師に施術を担当してもらう方が、安心ですし、尚且つ安全に考慮して施術をしてもらえます。
経験や技術力不足の医師が施術を行うと、リスクも高くなってしまうため、後悔しないためにも医師選びは大切です。
クリニックの選び方➁:アフターフォロー体制は整えられているか
骨切りはリスクが生じてしまうことから、万が一の時の事も考えて、アフターフォロー体制についてもしっかりとチェックしておきましょう。
施術後にも相談に乗ってくれたり、保証がしっかりとしているクリニックであれば、無償で再施術をしてもらえる可能性もあります。
クリニックの選び方③:カウンセリングは丁寧か
クリニック選びでは、カウンセリングの丁寧さもカギとなります。
どの施術を受けるにしてもクリニックでは必ずカウンセリングを行いますが、親身になって話を聞いてくれたり、施術のリスクやデメリットなどについてもきちんと説明してくれるクリニックであれば信頼できます。
逆に、リスクやデメリットには触れず、施術ばかりを勧めてくるクリニックであれば、信頼できるのでやめた方が良いです。
骨切り後のダウンタイム中は体温を上げすぎないことが鉄則!症状軽減のために気をつけよう

骨切りのダウンタイムをはじめ、期間中に現れる症状や術後の過ごし方などについて紹介しました。
ダウンタイム症状を軽減させるためにも、術後は気をつけるべきことがいくつかあります。
とくに、体温を必要以上に上げてしまうと内出血や腫れを助長してしまう恐れがあるため、十分に注意しながらダウンタイムを乗り切りましょう。
おすすめクリニック特集記事
あなたの目的別におすすめの美容クリニックを発表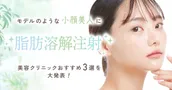
【二重あご解消】小顔脂肪溶解注射おすすめクリニック3選!顔の脂肪を1回で落とせるってホント?
89,880 views

【最短で小顔へ】顔の脂肪吸引おすすめクリニック5選!効果から口コミまで徹底比較!
54,216 views

【顔の脂肪吸引注射】おすすめクリニック3選を発表!顎下や頬の脂肪に効果があるってホント?
43,210 views

【2025年最新版】メーラーファット除去で小顔を目指す!おすすめ美容クリニック3選と施術内容・ダウンタイム・注意点を徹底解説
2,423 views

















